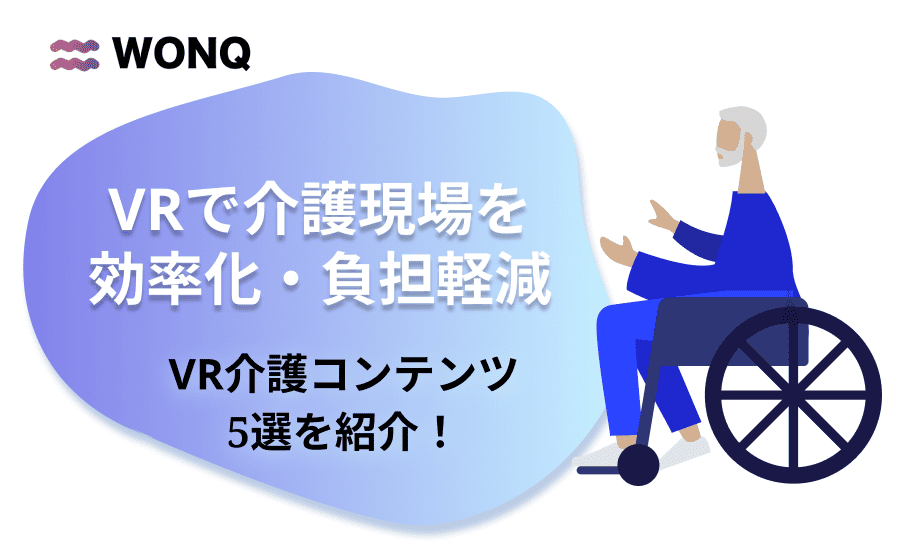本記事は、以下のようなお悩みを抱えている方に向けて書かれています。
「VRの制作をサポートしてくれる会社を探している」
「介護の現場でVRを使いたい」
「介護業界でのVR導入のメリットとデメリットが知りたい」
この記事では、VR介護の基礎知識やメリット・デメリット、おすすめVR介護コンテンツの比較、さらに実際の活用事例やよくある質問まで詳しく解説します。
VRイベントの導入を検討する企業担当者の方はぜひ参考にしてください。
介護の現場では人手不足や身体的・精神的負担が大きな課題となっています。
そんな中で注目されているのがVR介護です。
VR(バーチャルリアリティ)技術を活用することで、介護者は現実に近い仮想空間で実践的な研修やシミュレーションが可能になります。
また、被介護者にとっても新しい仮想体験が日常生活の刺激となり、リハビリの継続や外出体験に代わる効果が期待できます。
この記事では、VR介護の基礎知識からメリット・デメリット、具体的な事例まで詳しく解説します。
VR介護とは?
VR(バーチャルリアリティ)とは、コンピューターで作られた仮想空間に入り込み、あたかも現実世界にいるかのような体験ができる技術です。
専用ゴーグルやコントローラーなどの機器を使い、視覚・聴覚・触覚などを擬似的に刺激します。
介護分野ではこのVR技術を使って介護場面を再現し、研修やケアに活用する取り組みが広がっています。
例えば、VR内で転倒介助や認知症の疑似体験を繰り返し練習することで、ミスが許されない介護現場における対応力を高めることができます。
このようにVR技術を介護の現場に導入したものをVR介護と呼び、介護の質向上や効率化への効果が期待されています。
VR介護のメリット・デメリット
◉VR介護のメリット
1. いつでもどこでも研修できる: VRを使えば場所や時間を問わず介護研修が可能です。実際の介護施設を用意する必要がなく、オンラインで同じコンテンツを繰り返し受講できます。
2. 危険体験のシミュレーション: 転倒や緊急搬送など、現実では再現が難しい危険な状況もVRなら仮想空間で安全に体験できます。失敗しても影響がなく何度でも挑戦できるため、高い危機管理意識が養われます。
3. 介護者の理解が深まる: VRで要介護者の視点を体験することで、「なぜ利用者がこのような行動をとるのか」を介護者自身が実感できます。例えば認知症の方の視点をVR体験すれば、認知症行動の背景に理解が深まり、より丁寧なケアにつながると言われています。
4. リハビリ・外出疑似体験: 自宅から出にくい被介護者にはVRで旅行や外出体験を提供できます。没入型の景色や観光地の映像を体験することで、モチベーションを維持しながら自宅でリハビリに取り組めるメリットがあります。
◉VR介護のデメリット
1. 導入コスト: VRゴーグルや専用コンテンツの購入には初期費用がかかります。機器1台あたり数万円から十数万円、専用ソフトの開発・購入費用も発生します。多台数が必要な施設ではコスト負担が大きくなるのが課題です。
2. 操作習得の難しさ: 特に高齢者や機械に慣れていない介護職員にとっては、VR機器の操作を覚えるのに時間がかかる場合があります。ゴーグルの装着方法や操作に不安を抱く方もおり、慣れるまでは支援が必要です。
3. VR酔い・抵抗感: VRゴーグル装着による酔いや目の疲れを訴える人もいます。また「機械は苦手」という先入観からVR体験を嫌がる高齢者も少なくありません。無理強いせず、短時間体験から徐々に慣らす工夫が大切です。
おすすめVR介護コンテンツ5選
以下は介護分野で注目されているVRコンテンツやサービスの例です。
1. リハまる
介護施設向けのVRリハビリプログラム。手足を動かしながら遊び感覚でリハビリを行うコンテンツで、継続しやすい設計が特徴です。認知症予防や運動機能改善に効果が期待されています。

引用:リハまる
2. Floreo(フロレオ)
アメリカ発のVR療法コンテンツ。主に自閉症児支援で知られますが、高齢者向けにもソフトを応用可能です。VR空間で会話や交流の練習ができ、コミュニケーション訓練に活用されています。
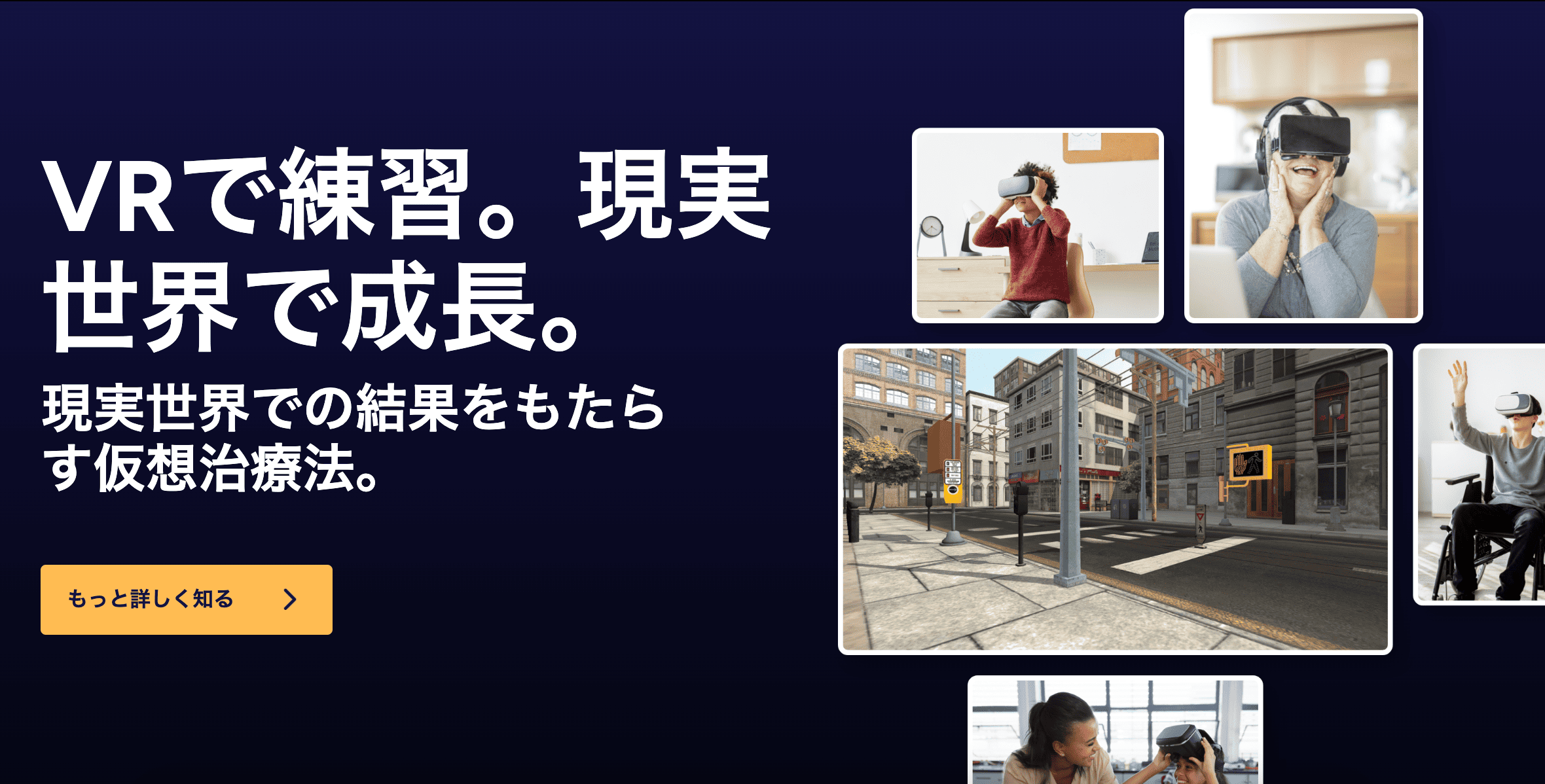
引用:Floreo(フロレオ)
3. Silverwood VR認知症体験
– 株式会社シルバーウッドの「VR認知症」プログラム。認知症の方の一人称視点を体験でき、介護スタッフや家族の理解を深めます。日本国内で延べ14万人以上が体験した実績があります。

引用:VR認知症
4. VR旅行プログラム
Google Earth VRや360度動画を活用し、自宅で世界各地を観光体験できるアプリ。
外出が難しい要介護者に疑似旅行を提供することで、気分転換や認知機能維持に役立ちます。

VR介護の導入事例
介護現場ではVR活用の事例が増えています。たとえば、企業向けに開発された認知症ケア支援VRでは、認知症の方の行動・気持ちを体験できる研修プログラムが2025年6月に公開されました。

引用:FACE DUO
認知症の方を介護されるご家族にとってはとても頼もしいサービスになるのではないでしょうか。
また、東京福祉保育専門学校など教育機関では、介護福祉士育成の一環としてVR研修が導入されています。他にも、先述のSilverwood VRやFloreoなど海外製コンテンツを導入し、介護力向上に取り組む施設が増えています。
よくある質問
Q: VR介護のメリットは?
A: VR介護では研修やリハビリを仮想空間で実施できるため、場所を選ばずリアルな体験が可能です。実際の危険な場面も安全にシミュレーションできるほか、認知症の視点体験で介護者の理解が深まる点などが挙げられます。
Q: VR介護のデメリットは?
A: 導入時にVRゴーグルや専用ソフトの費用が必要で初期投資がかかります。また、高齢者や機械に不慣れな方には操作習得に時間がかかり、VR酔いや抵抗感を示すケースもあります。これらに対応するため、無理なく慣らす工夫や補助者のサポートが重要です。
Q: VR介護でどんなコンテンツがある?
A: 介護スキル向上の研修用コンテンツや、認知症体験プログラム、VRリハビリ、VR旅行など多彩です。前述のSilverwood VR認知症やFloreoなど市販のサービスのほか、WONQのようにオーダーメイドで開発する選択肢もあります。
Q: VR介護導入の方法は?
A: まずVRヘッドセット(ゴーグル)を用意し、導入目的に合ったコンテンツを選びます。機器を購入するほか、レンタルや開発支援を利用する方法もあります。研修スタッフに操作説明を行い、少人数から導入するのが基本です。 WONQでは導入支援サービスも提供しており、お気軽にご相談ください。

まとめ
VR介護は新しい介護のかたちとして注目されています。被介護者の視点体験や楽しいリハビリ体験を通じてケアの質を高め、介護者の研修負担を軽減する効果が期待できます。一方で導入コストや運用には工夫が必要です。
私たちWONQでは、VR/ARの技術を活用して介護現場を支援しています。VR技術の導入を検討される方は、ぜひWONQの資料請求フォームやお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
VR介護でより効率的・安全な介護環境を実現しましょう。
 WONQスタッフ
WONQスタッフWONQのスタッフです。