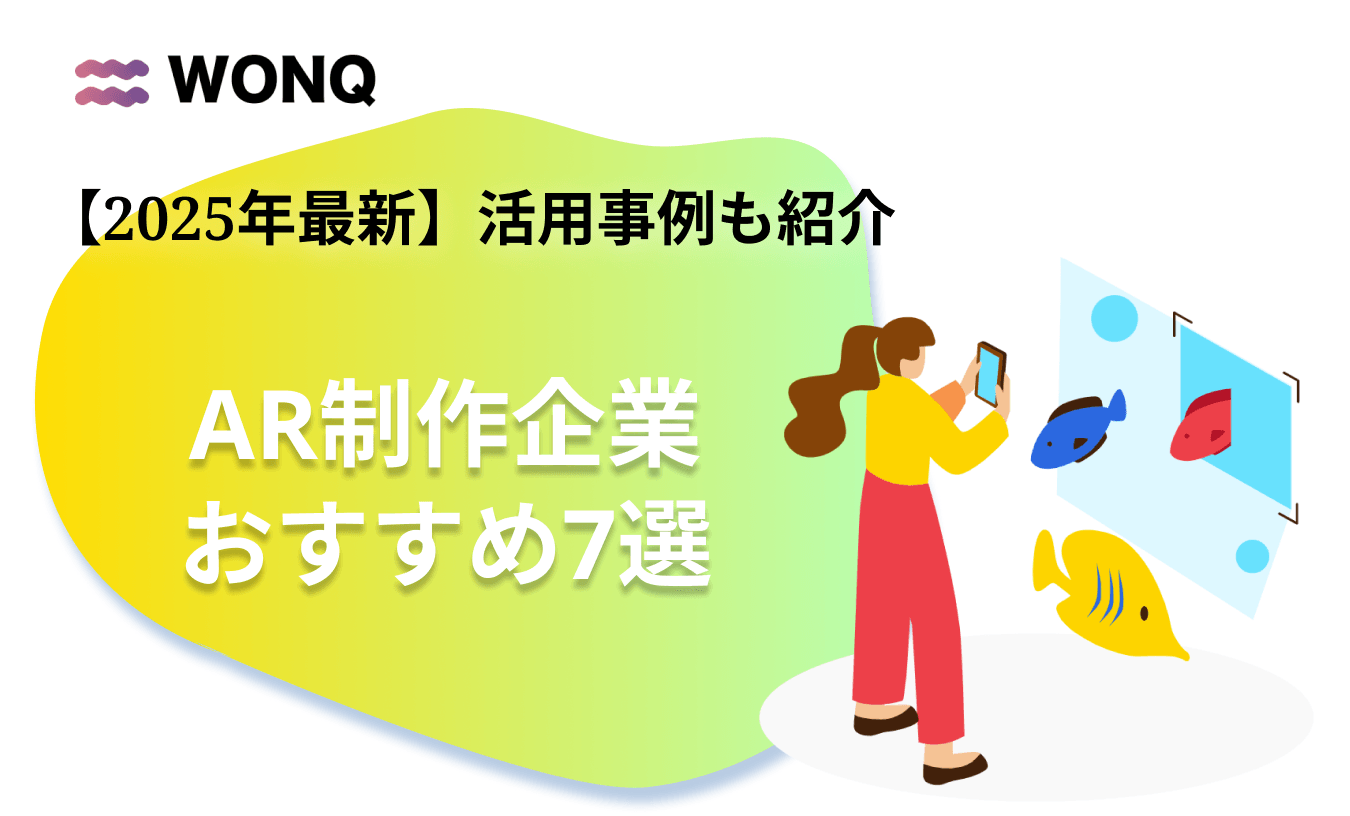本記事は、以下のようなお悩みを抱えている方に向けて書かれています。
「AR導入によるプロモーションや業務効率化のヒントが欲しい」
「ARを活用したプロジェクトを成功させたいが適切な制作会社を知りたい」
「AR技術の種類や特徴、自社に合った会社の選び方を理解したい」
「日本国内で信頼できるAR制作会社の事例や比較情報を知りたい」
本記事では、AR制作会社のタイプ分けからおすすめの企業一覧と特徴、依頼時の選定ポイント・注意点までをわかりやすく解説します。
AR制作を通じて効果的な顧客体験や業務改善を目指したい方はぜひご参考ください。
また、VR制作会社について知りたい方は下記記事をご覧ください。
2026年【VR制作会社10選】VRコンテンツ導入事例と費用相場
ARとは

AR(Augmented Reality, 拡張現実)とはスマートフォンやウェアラブルデバイスを通じて、現実空間にCGや情報を重ねる技術です。
プロモーションや業務効率化、教育、エンタメなど広範な分野で活用されています。
スマホのカメラで街並みをかざすと、その上にキャラクターが表示されたり、建物に関する情報が表示されたりするのがARの代表的な例です。
身近な例ではポケモンGOがARを使ったゲームとして有名です。 他にも、USJのアトラクションであるマリオカートや、スラムダンクの映画で配布された入場者特典もAR技術を使用したものになります。
今、注目される「AR制作会社」の種類

AR制作会社は大きく以下の3タイプに分類できます。
1. AR特化型
AR特化型の制作会社はAR技術そのものに深く精通しており、最先端の表現や高度なカスタマイズに強みを持っています。
例えば、WebARを用いたブラウザ上の体験、iOS/Androidアプリ向けのネイティブAR、さらにはARグラスやヘッドセット対応といった、幅広いプラットフォームに対応可能です。
こうした企業は技術的な精度や独自性が高いため、ブランド体験や製品PRを他と差別化したい場合に特に効果を発揮します。
ただし、各社によって得意分野が大きく異なるため、依頼前に強みを見極めることが成功の鍵となります。
尖った技術を武器に、唯一無二のAR体験を提供できるのがこのタイプの魅力です。
2. オールラウンダー型
オールラウンダー型はARに限らずVRやMRなど幅広いXR技術に対応できる制作会社を指します。
単一の体験ではなく複数のテクノロジーを組み合わせた複合型の体験を実現できる点が大きな強みです。
例えば、イベントではARで商品を試着しつつ、VRでバーチャル店舗を体験するといった統合的なプロモーションが可能になります。
また、企業の幅広いニーズに柔軟に対応できるため、XR戦略を中長期的に検討している企業にとって頼れるパートナーとなります。
多角的なアプローチで、ユーザーの体験価値を最大化できるのがこのタイプの魅力です。
3. ビジネスソリューション型
ビジネスソリューション型は単なる開発にとどまらず企画・設計・開発・導入・運用まで一気通貫で支援するタイプです。
ARを活用したいけれど具体的なアイデアや導入方針が定まっていない企業にとってコンサルティングに近い役割を果たしてくれる点が特徴です。
さらに、マーケティング戦略や事業目標と結びつけてAR施策を設計してくれるため、ROI(投資対効果)を重視する企業にも適しています。
導入後の運用サポートやデータ分析まで対応するケースも多く、長期的に事業へARを組み込むことを考えるなら有力な選択肢です。
ビジネス視点を強く意識した「成果につながるAR」を実現できるのが、このタイプの大きな魅力です。
日本国内で注目されるAR制作会社とその特徴
1. WONQ株式会社(オールラウンダー型)

WONQ株式会社は、福岡を拠点に法人向け完全オーダーメイドVR/ARソリューションを提供する会社です。
アジャイル寄りのスクラッチ開発で企画の段階からお客様のビジョンを丁寧にヒアリングし、文化財の魅力を最大限に引き出すVR/ARコンテンツの企画、システム開発、そして運用後の手厚いサポートまで、お客様のニーズに合わせた最適なVR/AR体験を実現をサポートさせていただきます。
AR導入による次世代体験創出にご興味のある方は、お気軽にご相談ください。
まずはお気軽に資料をご覧いただき、貴社の目的に最適なAR体験を、ぜひ一緒に実現しましょう。
2. 株式会社palan(AR特化型)

引用:株式会社palan
palanはpalanARなどのノーコード/ローコード型WebARプラットフォームを提供し、プログラミング不要でARコンテンツを短期間に作成・配信できる点が最大の強みです。
累計のAR作成数や導入社数が多く(公開されている最新データでは数万件・数千社規模の導入実績を掲げています)、自治体の観光施策や企業のプロモーション、展示会での体験提供など、幅広い汎用事例を持っています。
近年では大阪・関西万博など大規模イベントでのWebAR提供事例もあり、アプリ不要で来場者へスムーズに体験を届ける運用ノウハウを蓄積しています。
小〜中規模のキャンペーンや短期イベントでROIを重視する企業、アプリを介さずに幅広いユーザーにARを届けたいマーケターに向くサービスです。導入前のPoCから本番運用までスピード感を求める案件に向いています。
3. 株式会社STYLY(ビジネスソリューション型)

引用:株式会社STYLY
STYLY(旧Psychic VR Lab)は空間を身にまとうことを掲げる空間レイヤープラットフォームを中核にクリエイターコミュニティと連動したコンテンツ流通・受託制作を行っています。
プラットフォーム上には多数のクリエイターが参加しており、アート・ファッション・商業プロモーションなど、クリエイティブ寄りの空間演出に強みを発揮します。
官公庁や教育機関との協業実績もあり、クリエイター育成やロケーションベースのプロジェクトを通じて実運用ノウハウを持つ点が特徴です。
ノーコード的な編集性と、既存のコンテンツ流通基盤を活用したスケール化の両方を活かしたい企業に適しています。プラットフォーム×受託のハイブリッドで、アイディア重視の企画を実現したいケースに向いています。
4. アララ株式会社(ビジネスソリューション型)
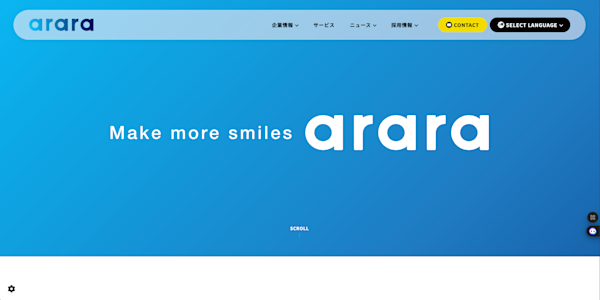
引用:アララ株式会社
アララは10年以上にわたるARサービス提供の実績を持ち、SNS向けARフィルターやWebAR、デジタルサイネージ連携など多様なフォーマットでの制作・運用ノウハウを備えています。
大手ブランドや博物館・商業施設などでの導入事例が豊富で、審査対応や配信後の運用・効果測定まで含めたフルサポートを提供できる点が顧客から評価されています。
特にSNS向けコンテンツや来館体験を拡張する展開に強く、短納期で安定的にリリースするための工程管理・テンプレ化が整っているのが強みです。
初めてARをキャンペーンに組み込む企業や、継続的な運用を前提にした導線設計を重視するプロジェクトに向いています。実績紹介ページで多様な業種の導入事例を確認できます。
5. モンスターラボグループ(ビジネスソリューション型)

引用:モンスターラボグループ
モンスターラボはグローバルな開発ネットワークを持ち、Web/モバイル/XRを横断する大規模なシステム構築とUX設計をワンストップで提供できる点が大きな特徴です。
企業のDX視点を併せ持ち、戦略立案からMVP開発、運用フェーズまでスケール感のある支援が可能であるため、ブランド横断のプロモーションや多拠点での導入を伴う大規模案件で選ばれることが多いです。
社内にはデザイン/開発/データ分析といった専門チームがあり、ARを体験だけで終わらせず、データ連携や業務改善に結びつける設計ができます。国際案件や多言語対応を要するプロジェクトにも対応できるため、海外展開を見据えたAR戦略に向くパートナーです。
6. 株式会社クロスリアリティ(オールラウンダー型)

引用:株式会社クロスリアリティ
クロスリアリティはVR/AR/MR を横断して扱う技術体制を持ち、教育機関や産業利用に向けたソリューション提供での実績が目立ちます。
米国のEON Reality との業務提携を通じてVRイノベーションアカデミー(VRIA)など人材育成やナレッジトランスファーの取り組みを推進しており、単なる制作会社にとどまらない教育・研修支援の価値を提供している点が特徴です。
産業向けトレーニングや教育カリキュラムと連動したXR導入を検討している組織にとって、技術移転や長期的な運用支援が期待できる存在です。
学習効果や定着を重視するプロジェクトに強みを発揮します。
7. 株式会社エム・ソフト(AR特化型/ビジネスソリューション型)

引用:株式会社エム・ソフト
エム・ソフトは国内5拠点・300名以上の技術者を擁し、長年にわたりAR開発の基盤技術であるARToolKitを扱ってきた実績を持ちWeb/マーカー型/マーカーレス/GPS型といった幅広いAR方式に対応できる点が大きな強みです。
国内に複数拠点を持ち、大規模案件や公共・産業用途の要件にも応えられる体制を整えているため、信頼性・保守性を重視する導入に適しています。
研究開発と実装の両輪で技術的な蓄積があり、カスタムセンサーや計測連携を含む業務支援系ARの案件でも強みを発揮します。長期運用や将来的な機能拡張を見越した設計・保守を望む企業に向くパートナーです。
制作会社を選ぶ際の5つのチェックポイント
1. 実績と業界経験
まず重視すべきは、その制作会社が過去にどのような実績を積み重ねてきたかという点です。
特に、自社と同じ業界や類似の目的で成功事例を持っているかどうかは重要です。
経験豊富な会社は、想定される課題やユーザー行動をあらかじめ理解しているため、プロジェクトの成功確率が高まります。
また、受賞歴や大手企業との取引実績などは信頼度を測る一つの指標になります。単に「ARが作れる」だけではなく、業界特有の文脈に精通しているかを確認しましょう。
2. 対応プラットフォーム
AR制作会社によって得意とするプラットフォームは異なります。
WebARであればアプリ不要で多くのユーザーに届けやすい反面、ネイティブアプリは高機能・高品質な体験を実現できます。
イベント用の大型ディスプレイやARグラス対応など、用途に応じた選択肢が求められる場面もあります。
そのため、自社の目的やターゲットユーザーに合致するプラットフォームを提供できるかを確認することが不可欠です。対応範囲が広い企業は柔軟な提案ができる点でも魅力的です。
3. 企画力・提案力
ARは「見せ方」次第で効果が大きく変わります。
そのため、ただ技術を実装するだけでなく、顧客体験をデザインする企画力があるかを見極める必要があります。
例えば、商品のAR試着を導入する際でも、どのように購買意欲を高めるか、SNSで話題化する仕掛けは何かといった視点で提案できる会社は頼りになります。
ヒアリング段階で自社の課題を理解し、目的に沿ったストーリーを描ける企業かどうかが重要です。技術力と企画力の両立が、成果につながるAR体験を生み出します。
4. サポート体制とコミュニケーション
AR制作は納品して終わりではなく、運用や改善が求められるケースがほとんどです。
そのため、リリース後の修正対応やバージョンアップ、運用支援がしっかり整っているかを確認しましょう。
また、制作過程でのコミュニケーションのスムーズさも非常に大切です。
チャットやオンライン会議で迅速に対応できる体制があれば、トラブル時にも安心です。
単なる外注先ではなく、共に事業を推進するパートナーとして信頼できるかを見極めましょう。
5. コスト・納期
最後に、コストと納期のバランスを見極めることも欠かせません。
初期の制作費用が安く見えても、実際には保守費用や運用コストが膨らむケースもあります。長期的に利用する場合は、トータルコストを明確に算出して比較することが重要です。
また、納期に関してはイベントやキャンペーンのタイミングに間に合うかどうかが成否を左右します。
無理のないスケジュールと予算で、安定した成果を出せる会社を選ぶことが理想です。
依頼までの流れ

1. 目的と対象ユーザーの明確化
まず社内でAR導入の“目的”を具体化します(例:販促での認知拡大/店舗での接客支援/現場教育の短縮など)。
誰に届けたいのか(年齢・デバイス所有率・利用シチュエーション=屋外/屋内)をペルソナ化し、KPI(到達数・滞在時間・購買転換など)を決めます。
関係部署(マーケ・営業・IT・現場責任者)を巻き込み、予算レンジやローンチ期日などの制約条件も早めに揃えておきます。
これらが曖昧だと提案の軸がブレるため、要件定義書にまとめて制作会社と共有できる状態にしておきましょう。
2. 対応プラットフォームの選定
ターゲットや目的に応じて、WebAR(ブラウザ)・ネイティブアプリ・ARグラス・館内端末(大型ディスプレイ)など最適な実行環境を選びます。
例えば、アプリ不要で幅広く届けたいならWebAR、複雑な空間把握や高精度な追跡が必要ならネイティブやグラスが向きます。
配信方法(ストリーミング/ダウンロード)やオフライン利用の可否、データ収集・分析の要件も設計段階で決めておくと見積り精度が上がります。
将来の拡張(多言語対応、機能追加)を見越して、プラットフォームの可搬性・保守性も評価基準に入れましょう。
3. 複数社での相談・見積り取得
企画書(目的・ターゲット・KPI・想定スコープ・期日・予算目安)を用意して、最低2〜3社に打診します。
見積りでは工程ごとの内訳、納品物(ソース・アセット・仕様書)、テスト・運用費、保守契約の有無を詳細に出してもらい、比較できるフォーマットで集めましょう。
実案件の事例、担当チームの顔ぶれ、スケジュールの妥当性、POC(試作)の可否も確認ポイントです。
機密性が高い場合は先にNDAを交わし、必要な場合はPoC費用の負担分や検証基準もあらかじめ取り決めておくと安全です。
4. 提案評価と担当者との相性確認
提出された提案を技術的実現性・UX設計・KPI達成見込み・コスト・スケジュールで総合評価します。
実機デモやプロトタイプがある場合は必ず確認し、想定対象者でのユーザーテスト(簡易でも可)結果を見て判断すると成功確率が上がります。
また、PMやクリエイティブ担当とのコミュニケーションの相性やレスポンス速度、意思決定プロセスの透明性も重要な判断軸です。
契約条件ではIP(著作権)・納期遅延時のペナルティ・保守レベル(SLA)・データ取り扱いを明確にしておきましょう。
5. 本制作 → テスト → 本番 → 運用・振り返り
開発はマイルストーン(要件確定→試作→中間レビュー→最終版)で管理し、各段階で成果物を検収します。
テストは機能・互換性(デバイス/OS)・パフォーマンス・UX(VR酔い抑制等)の観点で行い、ターゲットユーザーによるUAT(受入試験)を必ず実施します。
ローンチ後はアクセス解析や行動ログでKPIをトラッキングし、改善スプリントを回して効果を最大化。
さらに運用体制(保守契約、障害対応窓口、定期アップデート)と、成果をまとめた振返りレポートを作り次回施策に繋げましょう。
AR導入のメリットと注意点まとめ
ARを導入するメリットおよび注意点をまとめると下記の表の通りです。
メリット | 注意点 | ||
体験訴求が強力 | 商品や空間に視覚的情報を重ねることで、記憶への定着や理解度が高まる。 | 初期設計・UIの複雑さ | ユーザー動線や操作性の設計が必要。 |
コスト効率の改善 | パンフや展示物より柔軟にコンテンツ更新が可能。 | 環境・端末依存 | ARの動作環境(カメラ性能、通信回線、場所の明るさなど)に左右される場合あり。 |
リーチの拡張 | Web経由などで全国から体験可能に。SNS拡散にも強い。 | 運用負荷 | コンテンツ更新やデータ収集に伴う運用体制を考慮すべき。 |
まとめ:「目的に応じた最適なパートナー選びが鍵」
AR特化型は機能・技術の柔軟性重視の方におすすめです(例:palan、エム・ソフト)。
オールラウンダー型はXR領域を広くカバーしつつ、複合体験設計をしたい場合に最適です(例:WONQ、クロスリアリティ)。
ビジネスソリューション型は企画立案から導入まで手厚く支援してほしい企業に向いています(例:STYLY、アララ、MonstarLab)。

AR導入による次世代体験創出にご興味のある方は、お気軽にご相談ください。
まずはお気軽に資料をご覧いただき、貴社の目的に最適なAR体験を、ぜひ一緒に実現しましょう。
同執筆者による記事
【2026年最新】VR会議とは?メリット・デメリット、おすすめツール5選を徹底解説!
AI導入支援サービス10選を目的別に紹介 | 費用や補助金情報【2026年】
【2026年最新】 AI受託開発会社おすすめ25選!費用相場から選び方まで徹底解説
 Aso
AsoWONQ株式会社 システムエンジニア。
2024年12月にWONQ株式会社に入社。 入社後建築企業向け業務システムや塗装企業向けの基幹システムの構築など主にバックエンド側のシステム開発に従事。
現在はフロントエンドについて学習中。
プロフィール画像から分かる通り某対戦アクションゲームではカービィを使っている。