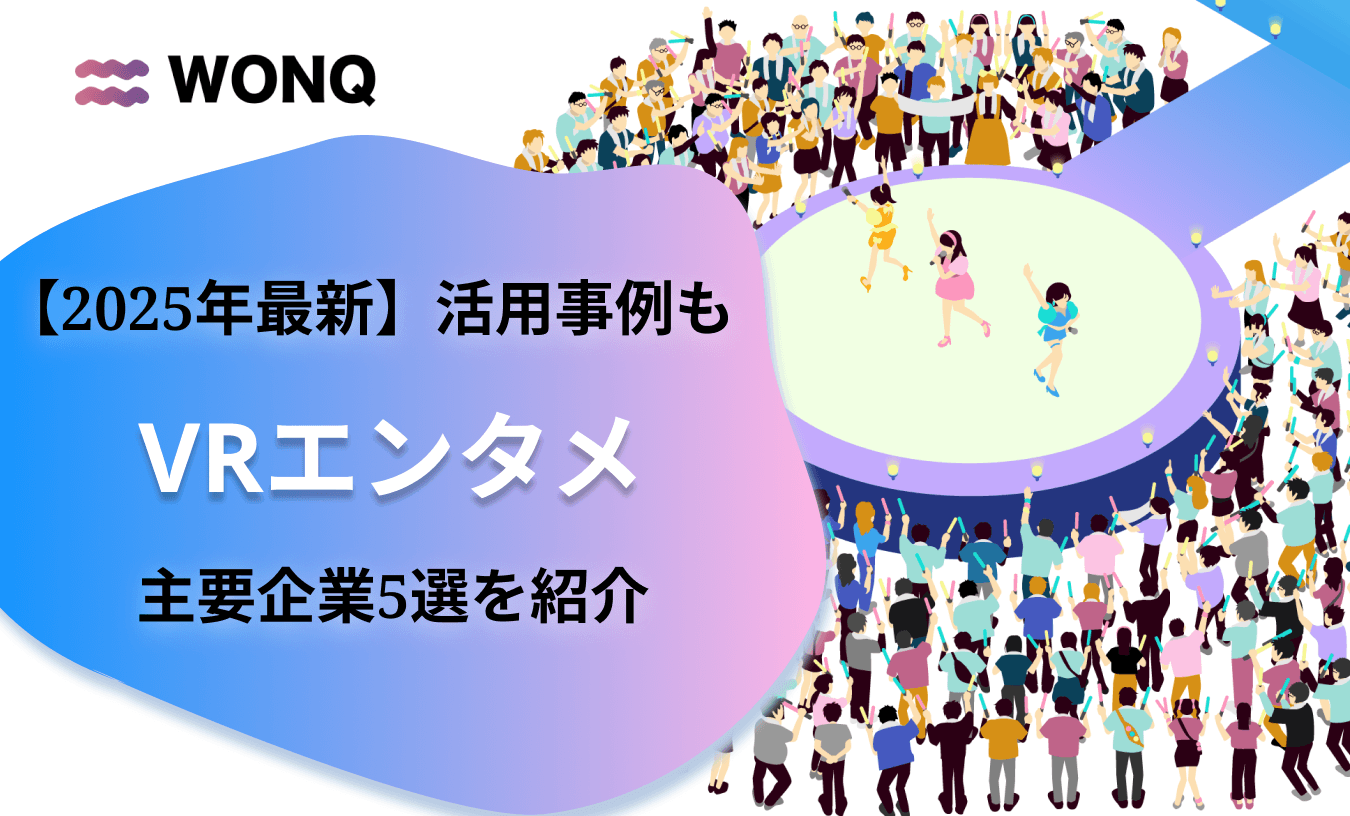ライブ、テーマパーク、スポーツ観戦。これらを次のステージへと進化させているのがVRエンタメです。
バーチャルリアリティ(VR)の進化は、観客の体験を単なる視聴から没入へと変えています。 しかし、
「VRでエンタメって具体的にどんなことができるの?」
「導入にはどんな企業が関わっているの?」
といった疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、VRエンタメの基本から最新の活用事例、そしてソリューションを提供する企業まで、徹底的にご紹介します!
ぜひ参考にしてください。
また、VRアトラクション制作を検討されている方は下記の記事を、
VRイベント企画についてご検討中の方は以下の記事をご参照ください。
VRイベント会社おすすめ8選【2026年最新】活用事例も紹介
VRとは?

VR(Virtual Reality, 仮想現実)とは見かけは現実ではないが、実質的には現実であること、現実の本質を有するもののこと
または、それがそこにないにもかかわらず観察するものにそこにあると感じさせる技術のことです。
エンタメ分野に近い具体例を2つ挙げると、テレビなどで紹介される際に見かける、Virtual Youtuber(Vtuber)という仮装空間上の
アイドルや高いところでの綱渡り体験がVRの具体例になります。
次に、エンタメの1つであるゲームとVRのつながりについて実例も交えて徹底解説してきます!
出典: バーチャルリアリティ学 p5
ゲームとVR

引用: グランブルーファンタジー X(旧ツイッター) グラブルフェス2025
VR技術の応用分野としてまず誰もが考えるのがゲームだと思います。
映像コンテンツを現在支えているのが映画産業やTV産業ですが、これはインタラクティブな映像ではありません。
この産業でインタラクティブな映像技術が要求されるのは製作段階であり、出来上がった製品そのものにVR技術が含まれることはありません。
つまり、いわゆるB2Bコンテンツしか期待できないわけで、その状態からユーザまでを本格的に巻き込んだB2CあるいはC2Cコンテンツにまで発展する必要があります。
今後この分野が大きな産業規模を持ちえるためには、インタラクティブな映像製品が必要になります。
その意味において、リアルタイムなコンピュータ映像を多用するゲームこそが、VR技術を存分に利用する応用分野として期待されています。
実際、後述するグランブルーファンタジーというソーシャルゲームにて年に数回開催されるグラブルフェスやグラブルEXTRAフェスにて騎空艇の室内等の架空世界にてキャラクターと触れ合える体験型アトラクションにもVRが活用されています。
出典: バーチャルリアリティ学 pp.348-349
VRエンタメとは?没入が生み出す新しい体験

VRエンタメとは、仮想現実技術を活用して観客やユーザーに圧倒的な没入体験を提供する新しいエンターテインメントの形です。
従来のテレビや映画のように画面を見るスタイルから一歩進み、観客自身が作品の空間に入り込んだかのような臨場感を味わえます。
360度視界に広がる映像と立体音響によって現実と錯覚するほどの没入感が得られるのが最大の特徴です。
近年はハードウェアの進化や通信環境の整備により一般ユーザーが手軽に楽しめる領域へと拡大しています。
今後はエンタメに限らず、教育やスポーツなど他分野との連携も進むことが期待されています。
主な活用形態
1.ライブVR
ライブVRはアーティストのコンサートや演劇をVR空間に再現し、まるで最前列にいるような体験を可能にするサービスです。
現地に足を運べないファンでも自宅にいながら臨場感あふれるステージを楽しむことができます。
さらに、視点を自由に切り替えたり、アーティストの近くに移動したりとリアルでは不可能な体験が実現されるのも大きな魅力です。
チケット販売や限定グッズとの連動によりVRならではの新しいビジネスモデルも広がっています。アーティストとファンをつなぐ「新しいライブの形」として注目が集まっています。
2.スポーツ観戦VR
スポーツ観戦VRはスタジアムの好きな座席を選んで観戦できるほか、選手目線のカメラ映像を体験できるサービスです。
通常の中継では味わえない「その場にいる感覚」を得られるため、観戦の価値を大きく引き上げます。
観客はゴールシーンをピッチサイドから体験したり、ベンチの近くで選手の声を聞いたりと、リアル観戦を超える没入感を楽しめます。
また、海外リーグや人気試合を自宅から観戦できるため、グローバルファンにとっても利便性が高いのが特長です。
将来的にはインタラクティブ要素を加え、仲間と一緒にVRスタジアムで観戦する時代が来ると考えられています。
3.テーマパークVR(IPA)
テーマパークVRはジェットコースターやシアター型アトラクションを仮想空間に再現し、リアル施設の拡張体験を提供します。
いわゆるIPAのことでIPA(Interactive Park Attractions)とはテーマパークで来園者の能動的な行動や操作によって体験内容が変化したり反応したりする体験型アトラクションのことを指します。
実際に施設を訪れることができない人でも、VRを通じてアトラクションを体験できるため、テーマパークの新たな魅力発信手段となっています。
さらに、VRと現地アトラクションを組み合わせることで「現実+仮想」の二重の楽しみ方が可能になります。
世界中の人気テーマパークでは、すでにVR専用コンテンツを導入する動きが加速しており、集客効果も期待されています。
エンタメ施設がオンラインとオフラインをつなぐ重要な要素として進化しているのです。
4.メタバース連携型エンタメ
メタバース連携型エンタメは、VRと仮想空間プラットフォームを融合させた次世代の娯楽体験です。
ユーザーはアバターを通じて世界中の人々と同じ空間に集まり、音楽ライブや映画上映をリアルタイムで楽しめます。
単なる鑑賞にとどまらず、仲間との交流やファン同士のコミュニティ形成が体験の中心となるのが大きな特徴です。
さらに、デジタルアイテムやNFTチケットの販売といった新しい経済圏も形成されつつあります。
メタバースとVRの組み合わせは、物理的距離を超えた「共体験」の価値を最大化する最前線のエンタメ手法として注目されています。
VRエンタメを支える主要企業
1. WONQ株式会社(VRコンテンツ開発)

WONQは、法人向け完全オーダーメイドのVR/AR開発を手がける専門企業です。
エンタメ業界もさることながら製造業・建設・医療・教育など幅広い業界を対象に、VRを活用した業務効率化ソリューションを企画・デザイン・開発・運用までワンストップで提供しています。
VR・ARだけでなくWebシステム制作も行うため、マルチプラットフォーム対応が可能なのが特徴です。
サンプル制作によるお試しプランも用意されており、まずは気軽に相談できます。
最新技術を活用したVRエンタメやイベント、VRコンテンツ導入のご相談はWONQにぜひお任せください!
2. 株式会社MyDearest(VRゲーム・ストーリーテリング)
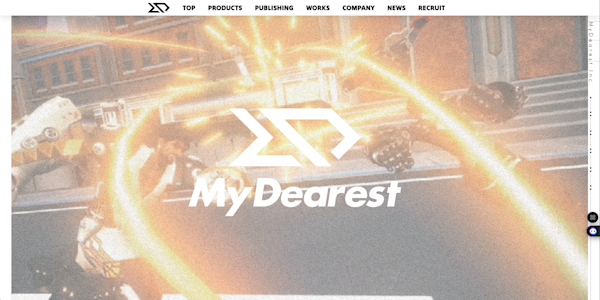
MyDearestは「物語体験」を重視したVRコンテンツの企画・開発を行う企業で、VR専用IPの制作・配信、ライセンスやマーチャンダイジングまで幅広く手がけています。
2016年設立で、ナラティブ志向のVRゲームを中心に据えた事業ポートフォリオを持ち、ユーザーの感情に響く没入型ストーリーテリングを強みとしています。
社内での開発体制に加え、外部パートナーとの協業によるIP展開や商品化も推進しており、VRコンテンツを軸にした長期的なIPビジネスを志向している点が特徴です。
コンシューマー向けのエンタメ性と、ファン層を育てる運営ノウハウを両立させたい事業者にマッチするパートナーです。
3. 株式会社バーチャルキャスト(バーチャルライブ配信)
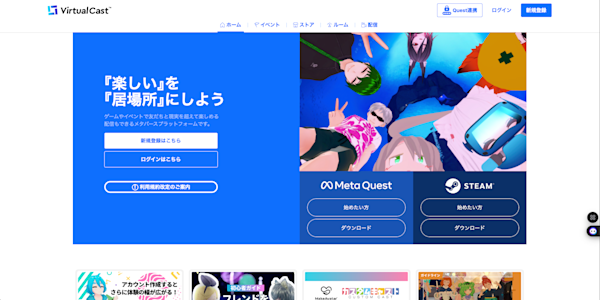
バーチャルキャストは、アバターを用いたソーシャルVRプラットフォームを提供し、ライブ、イベント、交流の場をオンラインで支えるサービスとして国内で広く利用されています。
ドワンゴとインフィニットループによる共同開発でスタートし、その後法人としてのサービス拡張を進め、VRライブやVTuberイベント、ユーザー生成コンテンツの流通機能などを実装しています。
最近はモーションキャプチャ機器やスマホ連携の取り込み、独自ストア機能の拡充などクリエイター支援を強化しており、コミュニティ運営と収益化を両立させたい企業に適しています。
イベント企画から配信基盤、3Dアセット流通までワンストップで導入できる点が魅力です。
4. Gugenka(XRコンテンツ開発)
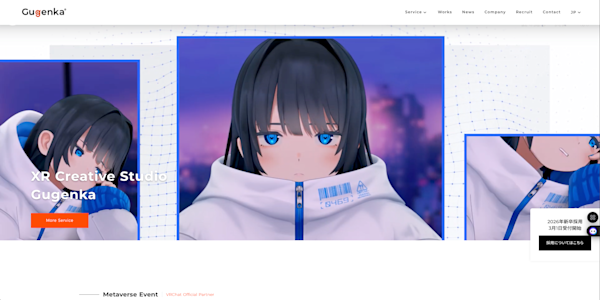
引用:Gugenka
Gugenka(グゲンカ)は、アニメ・マンガの公式IPを中心にXRコンテンツやデジタルフィギュア(HoloModels)を展開するプラットフォーム事業者で、キャラクター資産をデジタル商品として活用する取り組みが特徴です。
XMarketと呼ぶマーケットプレイスを通じて、公式デジタルフィギュアやAR/VR向けコンテンツを配信し、IPホルダーと協働した商流設計や二次収益化の仕組みづくりに実績があります。
3DCG制作力を活かした高品質なデジタルモデルの提供に加え、近年は企業買収や事業提携(2025年の株式取得報道等)を通じて事業基盤の強化を進めている点も注目されます。
特にキャラクターIPを活かしたファン向け体験やグッズ連動施策を検討する企業に適した選択肢です。
5. Epic Games Japan(Unreal Engineによる支援)
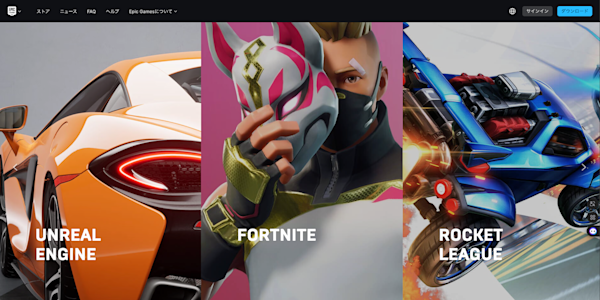
引用:Epic Games
Epic Games(日本法人を含む)は、Unreal Engineというリアルタイム3D制作ツールを通して、VRエンタメの開発基盤を提供しています。
Unreal Engineは高品質なグラフィックス表現と豊富なVRテンプレート/ドキュメントを備え、制作工数の短縮や表現力の向上に寄与するため、VRライブ演出や没入型ゲーム、ロケーションベース体験の制作に広く採用されています。
さらにEpicはパートナープログラムや技術サポート、開発者向けの学習リソースを提供しており、大規模プロジェクトや商用サービスの品質担保に有用です。
国内のエンタメ企業が高度な没入体験を目指す際の“技術基盤”として第一選択肢となるケースが多く見られます。
VRエンタメの最新事例
1.バーチャル渋谷(KDDI)

引用: バーチャル渋谷
バーチャル渋谷は、2020年5月に自治体公認で始まったメタバース空間で、渋谷区・KDDI・渋谷未来デザイン・渋谷区観光協会らが連携して開発されました。
スクランブル交差点やハチ公、渋谷の看板等、実際の渋谷のランドマークを高い忠実度で再現しており、ユーザーはアバターを使って自由に仮想渋谷を散策できるようになっています。
また「バーチャル渋谷・1DAYイベントパッケージ」というイベント主催者向けサービスがあり、ライブ・スポーツ観戦・トーク等を仮想空間上で実施でき、オリジナルアバターや演出なども含めたパッケージ提供がされています。 コロナ禍でリアルイベントが制約を受ける中、「場所に集まれなくても渋谷を体験できる」拡張空間として注目され、参加者との交流・ブランドコラボ・新規顧客接点としての活用が進みました。
ただし、常設で盛り上げを保つためには定期的なイベント開催が不可欠との声があり、非イベント時のアクティビティ設計やユーザーの参加維持が課題となっています。
2.乃木坂46 VRライブ

「乃木坂46 VRライブ」は、「いつか混ざりたいものです」というオリジナルVRコンテンツで、Xperia View用の差し込み型ヘッドセットで視聴できる形式です。
このライブコンテンツでは、楽曲「君に叱られた」のパフォーマンスを8K HDR 360度映像で撮影し、オリジナルフォーメーションでのステージが特徴となっており、ユーザーはメンバーに囲まれているような臨場感を味わいます。
「最前席より近い距離」と表現されるように、視聴者が実際にステージの中にいるような錯覚を抱かせることを意図した撮影・視点設計がなされており、VR酔いを抑えるための画角や視野の工夫も取り入れられています。
さらにこのコンテンツは期間限定視聴の特典として提供されたことがあり、ライブ配信ではなくあらかじめ録画された映像ながら、「VRによるプレミアムライブ体験」の実証例となっています。
このような形態はアーティストのファンにとって新しい接点を創出し、ライブ会場に足を運びにくいファン層へのアプローチなど拡張性の高い施策として評価されています。
3.ソニー「PlayStation VR2」対応ゲーム

引用: PlayStation VR2
PlayStation VR2(PS VR2)は、家庭用ゲーム機 PlayStation 5 向けのVRヘッドセットで、解像度、視野角、コントローラーの機能などが前世代から大幅に改良されていて、VRエンタメを大きく加速させるハードウェアです。
対応ゲームも多数あり、その中で特に注目されているのが『Horizon Call of the Mountain』や『グランツーリスモ7』など、自然の描写やアクションを重視した大作タイトルです。
例えば『グランツーリスモ7』ではレースゲームの臨場感がVRでより深く味わえるよう、視界の表現やコントローラー操作での没入感を重視した設計がなされており、多くのレビューでもVRモードの評価が高くなっています。
またPS VR2自体のハード仕様(OLEDディスプレイ、HDR対応、視野角・コントローラーの機能など)が、VR酔い低減や没入感向上に貢献しており、VRエンタメ体験の質を底上げしているとの声があります。
これは家庭用ゲーム機市場においてVRを本格的なエンターテインメントの選択肢とする転機と見なされており、ゲーム開発企業もPS VR2を視野に入れたタイトルを強化する動きが出ています。
4.グラブルフェス / グラブルEXTRAフェス VR体験

引用: グランブルーファンタジー X(旧ツイッター) グラブルフェス2025
グランブルーファンタジーはCygamesが開発しMobageが提供するスマートフォン向けソーシャルゲームで、東京に年1回グラブルフェス、地方で年に3-4回グラブルEXTRAフェスという大型イベントが開催されます。
グラブルフェス、グラブルEXTRAフェスの人気アトラクションの1つにVRコンテンツがあり、VRゴーグルとヘッドフォンを装着することで騎空艇の室内等の架空世界にてキャラクターと二人だけで過ごすことができます。
しかも、「VR四騎士」、「VR天司」、「VRガールズ」、「VRイーウィア」、「VRワムデュス」など年々コンテンツの種類が豊富になっています。
このVRコンテンツが大変凝っており、体験時に案内される室内とまったく同じ装飾の室内がVR内にて完全再現されているためリアルさを感じることができ、実際にキャラクターと触れ合うことで深い没入感にのめり込むことができます。
この体験型アトラクションのクオリティの高さや獲得できる臨場感や没入感、好きなキャラクターと触れ合うことができる点がファン層から非常に高く評価されています。
5.ザ・クリプト

引用: The Crypt
「ザ・クリプト(The Crypt)」とは1996年に東京ジョイポリスでSEGA(セガ)により公開されたCAVE型IPAです。
CAVEとは1992年にアメリカで発表されたVR技術、IPA(Interactive Park Attractions)とはテーマパークで来園者の能動的な行動や操作によって体験内容が変化したり反応したりする体験型アトラクションのことを指します。
当時セガはCAVEの技術情報を入手できなかったため、自社の毎秒15~30万ポリゴンが表示されるCGボード「MODEL2」と液晶シャッターメガネを用いることでCAVEと同様の機能を実現し、さらにそれを二人同時仕様に拡張したシステムを独力で開発しました。
「ザ・クリプト」にて地下の迷宮を通って財宝の部屋に入った観客は、岩石の巨人に頭をなぐられ、さらに地下深くまで落下します。
しかし観客は4畳半程度の小部屋から一歩も外には出ていません。
岩石の巨人も、壁と床面に映る影です。
部屋は「四周の壁と床」の5面が一辺2.7mの正方形のスクリーンで構成されています。
四つの壁面には背面から、床面には天井から立体映像が実時間で投影され、襲ってくる巨人の背後に観客が動けば、観客は巨人の背中を見ることができます。
「ザ・クリプト」が実現したインタラクティブ性は、圧倒的な臨場感を生み、これが話題となって終日二時間待ちの行列が長く続いたといいます。
出典: バーチャルリアリティ学 pp.272-273
6.「空気の港」展

引用: 「空気の港」展
2009年の10月から年末にかけて羽田空港の第一、第二旅客ターミナルにおいて実施された「空気の港」展はエンタメ業界のうちアート、すなわち芸術の分野へのVR技術の応用例となります。
空港という、本来であれば機能一辺倒のパブリックスペースに感性的価値を与えるための試みであり、普通であれば、抽象オブジェのようなパブリックアートがその役割を担いますが、そこに電子的手段を投入することができないだろうか、というもので、メディアアートの一つの発展の方向として注目を集めました。
この領域は、リアルな空間の演出を担当する建築計画の分割とVRをはじめとするデジタルメディア技術の境界領域ともいうことができます。
出典: バーチャルリアリティ学 p351
VRエンタメ導入のメリットと注意点まとめ
エンタメ業界におけるVRを導入するメリットおよび注意点をまとめると下記の表の通りです。
メリット | 注意点 | ||
|---|---|---|---|
距離や時間の制約を超える | 世界中どこからでも同じ体験を共有でき、新たなファン層の獲得に繋がります。 | 高品質コンテンツ制作のコスト | 3D空間や没入型体験の開発には多額の制作費が必要です。 |
新しい収益モデル | チケット販売やデジタルグッズ、アバター用アイテムなど新たなビジネスチャンスを生みます。 | VR酔いなど体験面の課題 | 最適化が不十分だとユーザーに不快感を与え、継続利用を妨げます。 |
差別化された体験提供 | 従来の配信サービスとは異なる没入感でブランド力の強化に直結します。 | 専門人材の不足 | VR開発に精通した人材が限られており、採用や育成に時間と費用がかかります。 |
ブランドイメージの革新 | 先進技術を活用することで「革新的な企業」としての認知を高められます。 | 高速通信環境の整備 | 大容量データを扱うため、安定した通信回線がないと体験品質に差が出ます。 |
まとめ
VRエンタメは、従来のエンタメの概念を大きく変え、観客の「鑑賞」から「参加」へと体験を進化させています。
導入には課題もありますが、ソリューション提供企業と連携することで、音楽、スポーツ、テーマパーク、ゲームといった幅広い領域で活用可能です。
これからのエンタメを形づくる鍵は、間違いなくVRにあります。
ぜひ、貴社のビジネスにVRエンタメの可能性を取り入れてみてはいかがでしょうか?
VR導入による次世代体験創出にご興味のある方は、お気軽にご相談ください。

まずはお気軽に資料をご覧いただき、貴社の目的に最適なVR体験を、ぜひ一緒に実現しましょう。
同執筆者による記事
【2026年最新】VR会議とは?メリット・デメリット、おすすめツール5選を徹底解説!
AI導入支援サービス10選を目的別に紹介 | 費用や補助金情報【2026年】
【2026年最新】 AI受託開発会社おすすめ25選!費用相場から選び方まで徹底解説
 Aso
AsoWONQ株式会社 システムエンジニア。
2024年12月にWONQ株式会社に入社。 入社後建築企業向け業務システムや塗装企業向けの基幹システムの構築など主にバックエンド側のシステム開発に従事。
現在はフロントエンドについて学習中。
プロフィール画像から分かる通り某対戦アクションゲームではカービィを使っている。